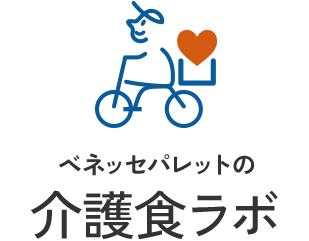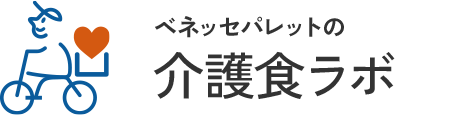2025 04 . 01
介護の基礎知識ゼリー粥とは?全粥との違いや作り方も
ゼリー粥はそしゃく力やお粥でも誤嚥してしまうなど飲みこむ力の弱った嚥下困難者や高齢者に向けた介護食として広く活用されています。この記事ではゼリー粥の特徴、全粥との違い、作り方や保存方法、市販品の選び方まで紹介。介護現場で役立つ情報をお届けします。

食事は生活の質を大きく左右するものです。そしゃく嚥下障害のある方でも安心して食べられる「ゼリー粥」は、やわらかい食感で、栄養バランスも取りやすい優れた介護食として注目されています。この記事では、ゼリー粥の基本情報から作り方、保存方法、市販品の選び方まで、介護現場で役立つ実践的な知識をご紹介します。

目次index
1.ゼリー粥とは?
ゼリー粥の定義と特徴
ゼリー粥とは、通常のお粥をゼリー状に加工した介護食で、主にそしゃく嚥下機能が低下した方や高齢者が安全に食事を楽しめるよう工夫された食事です。通常のお粥はやわらかく飲み込みやすい食品として知られていますが、そしゃく嚥下機能が著しく低下している方には誤嚥防止などさらなる安全性が求められます。そこで役に立つのがゼリー粥です。
ゼリー粥の特徴として主に3つのポイントがあげられます。
食べやすさ:ゼリー状にすることで、固形状のまま崩れず、口の中で滑らかに動き、飲みこみがスムーズになります。
適応範囲の広さ:そしゃく嚥下機能の低下が軽度の方から重度の方まで、幅広い状態に対応できます。
栄養補助:ベースとなるお粥に栄養剤やビタミン、タンパク質を追加することで栄養不足の補助ができます。
介護食としての重要性
高齢になるとそしゃく嚥下機能の衰えから、食事中の誤嚥の危険性が高まるほか、食事量の減少などによって、栄養不足や脱水につながる危険性もあります。その点ゼリー粥は、そしゃく嚥下機能に障害があっても安心して食べられるうえ、栄養価を補いやすく、介護現場で広く採用されています。
また、ゼリー粥にだしやスープなどでうま味を加えるなど、味や香り、見た目の工夫をすることでそしゃく嚥下機能が低下している方でも、食事を楽しんでいただけるように支援できます。
2.全粥との違い

ゼリー粥と全粥は、どちらもお米を使ったやわらかい食事形態です。しかし、それぞれの特徴や適用場面には大きな違いがあります。以下では、ゼリー粥と全粥の違いをご紹介します。
食感と嚥下のしやすさ
全粥は、炊いたご飯を水分多めでやわらかく煮込んだものです。形状はやわらかく、食べやすいですが、粒の形が残っているため、口や喉の動きが正常な方に向いています。一方で、ゼリー粥は、全粥をゼリー状に加工した食事形態。粒がなく、均一な滑らかさを持ちます。ゼリー状にすることで、気管への誤嚥を防ぎやすく、飲み込みやすいのが特徴。嚥下機能が低下している方でも安全に食べられます。
| 全粥 | ゼリー粥 | |
|---|---|---|
| 粘度 | 低い | 高い |
| 食感 | 米粒感あり | 滑らか |
| 誤嚥リスク | 一般的 | 低め |
栄養面の違い
全粥はご飯そのものの栄養価を保持しているため、糖質が中心ですが、ゼリー粥ではゼリー化の過程で栄養強化や味付けが可能です。必要に応じてタンパク質、ビタミン、ミネラルを添加することで、1食でより不足しがちな栄養素を補う食事としても加工がしやすく、バランスの取れた食事を提供できます。
3.ゼリー粥の作り方
簡単な作り方とゼリー化のコツ
〈材料〉
全粥またはおかゆ
ゲル化剤
〈作り方〉
1.全粥を用意し、ブレンダーで滑らかにする。
2.指定された量のゲル化剤を加え、固める。
作り方のコツ: ゲル化剤の種類によって、固める温度や使用量が異なります。適量・適温を守ることで、失敗せずにゼリー粥をつくることができます。
4.市販品の選び方
ゲル化剤を用いて手作りするだけでなく、最近は、市販品も多数販売されているため、活用するのもひとつの手。単純に全粥をゼリー化したものから、味付けに工夫のあるもの、栄養価を添加したものなどが出ているため、用途に合わせて選ぶことができます。
選ぶ際のチェックポイント
成分表示:添加物やアレルゲンの有無を確認。
栄養価:必要なカロリーやタンパク質を補えるか。
食感:食べる人に合わせたやわらかさや滑らかさになっているか。
使いやすさ:個包装やレンジ対応タイプなど、使いやすさや加熱の簡便さが適当か。
ゼリー粥はそしゃく嚥下機能が低下している方にとって安全で食べやすく、栄養補給の手段としても優れた選択肢です。個々人の状態に合わせて、ゼリー粥の提供をぜひ検討ください。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい