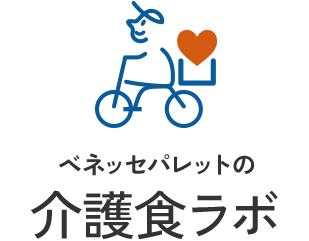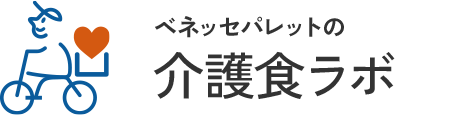2025 07 . 02
高齢者の栄養高齢者の低栄養を防ぐ 栄養管理のポイント
高齢者の低栄養を防ぐために必要な栄養管理のポイントを解説します。具体的な栄養素、リスク要因、実践的な対策について紹介します。

高齢者の低栄養を防ぐためには、日常生活の中でできる栄養管理が求められます。そこで具体的な食事の工夫やサポート方法についてご紹介します。

目次index
1.高齢者の低栄養を防ぐ栄養管理のポイント
高齢者の低栄養は、健康維持や生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼします。そこで厚生労働省の指針を踏まえ、高齢者の栄養管理における基本方針と対策方法をお伝えします。
低栄養の原因とリスク
年を重ねることで、体の様々な機能が低下。食事量が減少することで、栄養不足を招く恐れがあります。
嚥下機能の低下:飲み込みが困難になり、食事量が減少することがあります。
消化機能の低下:胃腸の働きが鈍くなり、栄養素の吸収効率が低下します。
食欲の減衰:味覚や嗅覚の鈍化、心理的な要因で食欲が低下するケースも少なくありません。
また経済的理由だけでなく、過度な偏食や独居で調理が面倒になることなどから、栄養不足に陥ることもあります。
上記のようなことから低栄養が進行すると以下のようなリスクが発生します。
フレイル(虚弱):身体能力が低下し、疲れやすくなる。
サルコペニア:筋肉量が減少し、転倒や骨折のリスクが上昇。
寝たきり:転倒や骨折がきっかけで生活の自立度が低下する。
厚生労働省における指針と具体的な対策方法
厚生労働省は、フレイル予防や栄養管理に対して具体的な指針を提示しています。
1日3食の摂取:食事を規則的に取ることで、安定した栄養供給を確保。
主食・主菜・副菜のバランス:これらを1日2回以上含む食事が推奨されます。
多品目摂取:20品目以上の食品を目指し、多様な栄養素を取り入れる。
2.高齢者の健康維持に必要な栄養素

高齢者が健康を維持するのに重要なのは、いかに筋肉量を保持し、いつまでも行動できる状態でいるかです。そのために重要なのが、たんぱく質とエネルギーです。
たんぱく質の重要性
たんぱく質は筋肉や臓器を構成する重要な要素です。しかし、高齢者は消化吸収能力が低下するため、たんぱく質が不足しやすい傾向があります。
推奨量:体重1kgあたり1.0~1.2gのたんぱく質が推奨されています。
エネルギーの重要性
エネルギーは脳や体が動くのに欠かせない栄養素。不足すると、筋肉を分解してでもエネルギーを補充しようとします。
特に高齢者は日中の活動量が減少しやすく、結果、食事量が減り、トータルでの摂取カロリーが不足しやすくなります。食事量が減ったり、そしゃく嚥下機能が弱まることで、固形物が摂りづらくなったりした場合は、同じ1gでもよりエネルギー量の多い脂肪(油)で補うなど、炭水化物と脂肪のバランスを意識するとよいでしょう。
栄養ケア・マネジメント
栄養ケア・マネジメントとは、高齢者の栄養状態を的確に評価し、適切な介入を行うことで健康状態の維持・改善を目指すプロセスです。病院や高齢者介護施設では、栄養士や管理栄養士を中心としたチームで取り組むことが一般的です。
〈栄養ケア・マネジメントのプロセス〉
栄養ケア・マネジメントは、主に以下の4つのステップで構成されます。
スクリーニング
栄養状態のリスクがあるかを評価。一般的には以下の指標が用いられます。
BMI(体格指数):18.5未満は低栄養リスクの可能性。
体重減少:1か月で5%以上の減少がある場合はリスク。
食事摂取量:通常の50%以下しか食べていない場合は要注意。
栄養アセスメント
詳細な評価を行い、介入が必要かを判断します。
身体データ:体重、身長、握力などの測定。
生化学データ:血清アルブミン値(3.5g/dL未満は低栄養リスク)、総コレステロール値など。
問診:食事内容、嚥下能力、生活習慣の把握。
栄養ケア計画の策定
アセスメント結果に基づき、個別の栄養ケアプランを作成します。
食事の具体的内容:たんぱく質強化食品の利用、カロリー補充のための間食の提案。
摂取方法の工夫:嚥下障害がある場合はソフト食やペースト食を推奨。
目標設定:例えば、「体重を落とさない」、「1か月以内に体重を500g増加させる」などの具体的な目標。
実施とモニタリング
計画に基づき、栄養ケアを実施。同時に定期的なモニタリングを行い、必要に応じて計画を修正します。
モニタリング頻度:週に1回程度の体重測定や月1回の血液検査が推奨されます。
フィードバック:チーム内での共有と、家族への報告を行います。
栄養ケア・マネジメントは、一人の専門職だけではなく、多職種連携が鍵となります。
栄養士・管理栄養士:栄養計画の作成、食事内容の提案。
看護師:食事摂取状況の確認や体調変化のモニタリング。
介護士:食事介助や日常生活でのサポート。
医師:全体の健康状態の監督と治療方針との整合性確認。
高齢者の栄養管理は、単なる食事の提供にとどまらず、個々のニーズに合った工夫と計画が必要です。低栄養のリスクを理解し、栄養管理を行うことで、高齢者の健康と生活の質を向上させることができます。
参考文献:厚生労働省「健康日本21」
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。