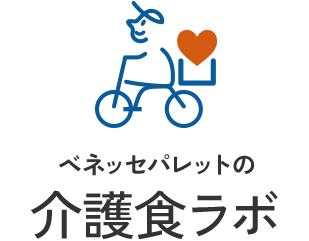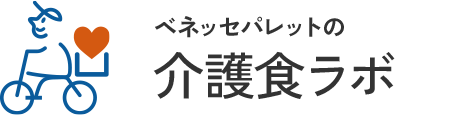2025 08 . 13
介護の基礎知識介護食士とは?資格の取り方・仕事内容をわかりやすく解説
介護食士は高齢者向けの食事づくりに必要な知識と技術を学ぶ資格です。取得方法や活躍の場、他の資格との違いを紹介します。

高齢化が進む中、介護が必要な方への食事提供のあり方にも注目が集まっています。特に「噛む力」や「飲み込む力」が弱くなった方に向けて、安全でおいしく、栄養バランスのとれた食事を提供するには、専門的な知識と工夫が不可欠です。
こうしたニーズに応える知識と技術を習得できるのが「介護食士」という民間資格です。
この記事では、「どんなことを学べるの?」「取得するとどんな場所で活かせるの?」「ほかの資格とはどう違うの?」といった、気になるポイントをわかりやすくまとめてご紹介します。

目次index
介護食士とは?

介護食士は、公益社団法人全国調理職業訓練協会が運営する資格であり、取得することで介護が必要な方向けに食事を提供する際に必要な知識や技術を有していることが証明できます。食材をただ 単にやわらかくするだけでなく、粘度・かたさ・形・味つけを工夫し、見た目や食感にも配慮した調理を行います。
この資格は、内閣総理大臣から許可を受けた公益社団法人 全国調理職業訓練協会によって認定されており、介護や医療の現場で実践的に活かせるスキルを体系的に学べるのが特徴です。高齢化が進む今 だからこそ「食の専門家」としての役割が注目されています。
介護食士の役割
介護食士は、介護を必要としている方に食事を提供するだけでなく、調理技術や栄養の知識を活かして、利用者が安全に、そして楽しく食べられる環境づくりを目指す資格です。具体的には、利用者の身体状況に合わせて食事形態を細かく調整し、見た目や香りに工夫を加えて食欲を高めるなど、食事の時間をより豊かにする役割も担います。
介護食士はどんな職場で活かせる?
介護食士の知識や技術は、以下のような職場で役立つとされています。
● 特別養護老人ホームや介護老人保健施設
● 病院やリハビリテーション施設
● グループホームや福祉施設
● 在宅介護の訪問サービス
● 配食サービスや給食センター
これらの現場では、栄養士や調理師、介護福祉士と連携しながら、安全でおいしい介護食の提供が求められます。
【介護食士】資格の種類とステップアップ
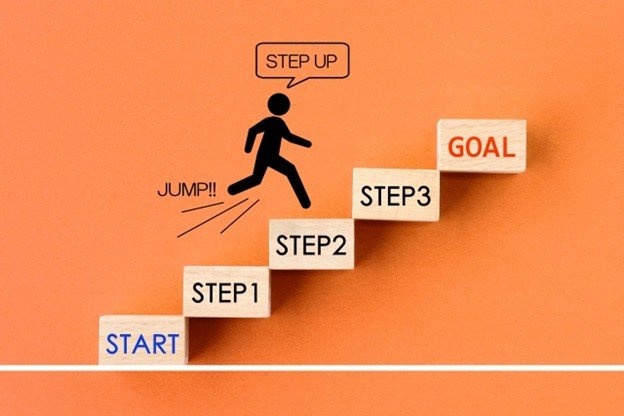
介護食士の資格は3級から1級まであり、段階的にスキルを向上させることができます。習得レベルに応じて、現場での役割も広がるのが特徴です。
介護食士3級〜1級の違いとレベル感
介護食士資格の3級から1級までのレベルについては、以下のとおりです。
● 3級:高齢者の身体特徴や栄養、衛生の基礎知識に加え、食べやすい介護食の調理技術を学ぶ初心者向けの入門レベル
● 2級:医学的知識や高齢者の心理、食材衛生を学び、普通食から介護食への展開や生活習慣病予防食の調理ができる実践レベル
● 1級:栄養状態の判定や疾病に応じた献立作成、薬との関係を理解し、多様な利用者に対応した献立管理や調理指導ができる上級レベル
ステップアップにより専門性が深まり、現場での責任範囲も広がります。
国家資格でなくても現場で重宝される理由
介護食士は国家資格ではなく、民間資格ですが、調理師養成校や福祉関連の教育機関で介護食に関する知識と技術を学ぶための講座として採用されており、現場で役立つ人材を育成する資格として認識されています。
近年、超高齢社会が進む中で、高齢者のそしゃく・嚥下機能の低下、低栄養といった問題への対応がより重要になっています。その背景の一つとして、厚生労働省の「令和6年(2024年)人口動態統計月報年計」にもあるように、誤嚥性肺炎が高齢者の主な死因の一つになっていることがあげられます。また、「令和5年(2023年)の国民健康・栄養調査」では、85歳以上でBMI20未満の低栄養傾向が特に顕著となっています。
こうしたことから、介護食の専門知識と技能を持つ人材の需要は、今後さらに高まると考えられます。介護施設や医療機関だけでなく、家庭や地域など幅広いシーンで介護食士の役割がより重要になっていくでしょう。
【介護食士】資格の取り方

介護食士の資格は、講習会に参加することで取得できます。講習は公益社団法人全国調理職業訓練協会の公式ホームページに掲載されている、全国の調理師専門学校や福祉関連教育機関で開講されています。開催時期や会場、費用は施設ごとに異なるため、詳しくは各施設へ直接確認することをおすすめします。
ここでは取得方法と各級の講習内容についてご紹介します。
資格の取り方
介護食士資格を取得するには、以下のいずれかの方法で講習を受ける必要があります。
● 教育機関の課程に組み込まれている場合(学生対象)
● 一般向けに開講される講習会に参加する場合(社会人・施設職員など)
講習は「学科」と「実習」で構成されており、高齢者の身体的特徴や栄養学、衛生管理、介護食の調理技術などを学びます。
各級の講習内容
介護食士の各級の講習内容は以下のとおりです。
3級
● 受講条件:誰でも受講可能
学科(25時間):介護食士概論、医学的基礎知識、高齢者の心理、栄養学、食品学、食品衛生学
● 実習(47時間):調理理論・調理実習Ⅰ、調理理論・調理実習Ⅱ
2級
● 受講条件:介護食士3級の取得者
学科(16時間):医学的基礎知識、高齢者の心理、栄養学、食品学、食品衛生学
● 実習(56時間):調理理論、調理実習
1級
● 受講条件:介護食士2級を取得後に、2年以上の実務経験がある25歳以上の者
● 学科(32時間):医学的基礎知識、高齢者にかかわる制度、栄養学、食品学、食品衛生学
● 実習(40時間):調理理論、調理実習
出典:公益社団法人 全国調理職業訓練協会「介護食士講座・資格の種類」
介護食士のキャリア・年収・他資格との比較

ここでは、介護食士という資格がキャリア形成や年収にどのように関わっているのか、また他の関連資格と比較してどのような特徴があるのかを解説します。
介護食士の平均年収と収入への影響
介護食士は民間資格のため、収入に直結するよりも、現場での実務力や信頼性の裏づけとして評価される傾向があります。資格単体の平均年収に関する公的なデータはありませんが、調理師や福祉系の職に就いている方が取得していることが多いといわれており、職種に応じた収入の中に反映されていると考えられます。
働く施設の種類や地域によって収入に差はありますが、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、病院や介護施設で働く調理スタッフの年収はおおむね350万円前後です。さらに、介護福祉士や栄養士など他の資格と組み合わせると、キャリアアップを図りやすくなり、給与アップも期待できます。
また、一般の方でも、介護食士と実務経験を組み合わせることで、高く評価される場合があります。このように現場での信頼性向上やスキルの証明として、収入面にもプラスに働くと考えられるでしょう。
栄養士・調理師・介護職員初任者研修などとの違い
介護食士は、現場で栄養士や調理師、介護福祉士、介護職員初任者研修の修了者などと連携しながら、利用者の状況に合わせた食事や介護サービスを提供しています。
介護と食にまつわる資格とその特徴を以下にまとめたので参考にしてください。
|
資格名 |
種類 |
主な役割・特徴 |
|
介護食士 |
民間資格 |
そしゃくや嚥下を考えた食事の調理技術に特化 |
|
管理栄養士・栄養士 |
国家資格 |
栄養バランスの献立作成と栄養指導を担当 |
|
調理士 |
国家資格 |
衛生管理を含む調理全般を担当 |
|
介護福祉士 |
国家資格 |
身体介護や生活支援など介護全般を担当 |
|
介護職員初任者研修 |
民間資格 |
利用者の自宅で生活支援や身体介護を行う |
【まとめ】介護食士は現場力を高める専門資格

介護食士は、高齢者に安全で栄養バランスの良い食事を提供し、生活の質を向上させるのに欠かせない専門資格の一つです。国家資格ではありませんが、現場での実践力が評価されやすく、3級から1級まで段階的にスキルアップが可能です。これから介護食の専門性を高めたい方や介護・調理の現場でキャリアアップを目指す方は、資格取得を検討してみてはいかがでしょうか。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい