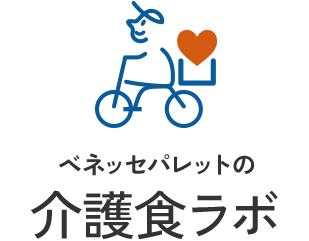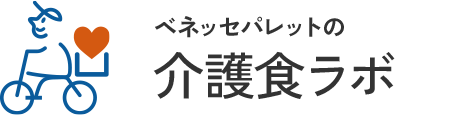2025 09 . 10
介護の基礎知識介護食アドバイザー資格とは?メリット・取得方法・活かし方を徹底解説
高齢者の安全でおいしい食事を支える「介護食アドバイザー資格」を徹底解説。取得方法や通信講座の学習内容、試験情報、活かし方まで、家庭や施設、地域活動で役立つ実践的スキルをわかりやすく紹介します。

高齢化が進んでいる日本では、食事支援の重要性が高まっています。そしゃく嚥下機能が弱くなった高齢者にとって、食事は栄養補給だけでなく生活の楽しみでもあります。そうした背景から注目されているのが介護食アドバイザー資格です。
介護や福祉の現場はもちろん、家庭介護や地域活動でも役立つこの資格について、概要やメリット、取得方法、活かし方を解説します。

目次index
介護食アドバイザーとは?
介護食アドバイザーは、高齢者や要介護者が安全に、そしておいしく食事を楽しめるように、知識と技術を身につけることを目的とした、一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)認定の民間資格です。 基礎から応用まで体系的に学べるため、介護・医療・福祉関係の方はもちろん、飲食業界の方のプラスαの知識としても推奨されています。
介護食アドバイザー資格で学べる内容
この資格では、高齢者の身体機能や食事に関する基礎から、実践的な調理法まで幅広く学習できます。具体的には以下のような分野です。
● 高齢者の心理
● 高齢者の生理機能の老化
● 栄養素摂取のポイント
● 高齢者の体の特徴と食事の関係
● 誤飲防止のポイント
座学だけでなく、調理や献立づくりに活かせる実践的な知識が学べるのが特徴です。
【出典】一般財団法人 日本能力開発推進協会「介護食アドバイザー」
https://www.jadp-society.or.jp/course/care-food/
国家資格との違い・民間資格としての位置づけ
介護食アドバイザーと似たような資格で、よく耳にする管理栄養士や介護福祉士は国家資格であり、特定の職業に従事するために必要な知識・技能・能力を証明する資格です。
一方、介護食アドバイザーは民間資格であり、特定の職務に従事するために必須の資格というわけではありません。つまり、介護食アドバイザーは高齢者の食事に特化した、実践的スキルを証明する資格であり、スキルアップに役立つ資格となっています。
他の介護食関連資格との違い
介護食関連の資格には、介護食士、介護食コーディネーターなど複数の民間資格があります。それぞれの違いを整理すると以下のようになります。
介護食士:調理技術に重点。3級~1級まで段階的に学べ、施設など専門職向けの内容が中心。
介護食コーディネーター:献立作成や栄養バランスを中心に学ぶことができ、家庭や地域活動で安心かつおいしい介護食づくりに活用可能。
介護食アドバイザー:高齢者の心理や身体機能の理解から誤嚥防止、調理の工夫まで幅広く学べるのが特徴。家庭介護はもちろん、介護・医療・福祉現場や飲食業界でも実践的に活かしやすい。
中でも、介護食コーディネーターと介護食アドバイザー資格は、初心者でも取り組みやすく、家庭介護やボランティア活動に役立つ入門資格として注目されています。
介護食アドバイザー資格がおすすめの人

介護食アドバイザーは、家庭や施設、地域活動など、さまざまな場面で役立ちます。こんな方に特におすすめです。
●家庭介護に従事している方:毎日の食事作りにすぐ役立つ実践的な知識が身につきます
●将来に備えて学びたい方:いざというときに安心して対応できるスキルが得られます
●地域活動やボランティアに関わる方:食事面から高齢者支援に貢献できます
●介護職や調理スタッフ:提供する食事の質を高め、仕事にも活かせます
学んだ知識は日常の食事作りや施設での業務にすぐ活かせるため、無理なく取り組めるのが魅力です。
介護食アドバイザー資格を取得するメリット
介護食アドバイザー資格を取得することで、家庭や施設、地域活動などで役立つ実践的な知識とスキルを体系的に身につけることができます。ここでは、特に注目すべき3つのメリットを紹介します。
体系的な知識とスキルが身につく
自己流の介護食作りでは、栄養バランスが偏ったり、安全性の懸念があったりする場合があります。資格を通して学ぶことで、そしゃく嚥下機能に合わせた調理法、見た目や味の工夫、栄養管理の基本を体系的に習得できます。知識と実践の両面から支えられるため、家族や利用者に安心して食事を提供できるのは大きなメリットです。
キャリア面での価値向上
介護施設や福祉事業所で働く場合、「介護食に関する知識を持っている」ことは大きな強みになります。履歴書や職務経歴書に記載することでアピールでき、採用や評価にプラスに働くこともあります。特に調理スタッフや介護スタッフの採用においては、即戦力として歓迎されやすい資格といえるでしょう。
生活全般や地域活動での活用
介護食アドバイザーは、家庭介護の場面だけでなく、地域の高齢者サロンやボランティア活動、料理教室など幅広い場面で活かせます。食事を通して交流を深めることで、地域貢献につなげられる点も魅力です。
介護食アドバイザー資格の学習の流れ
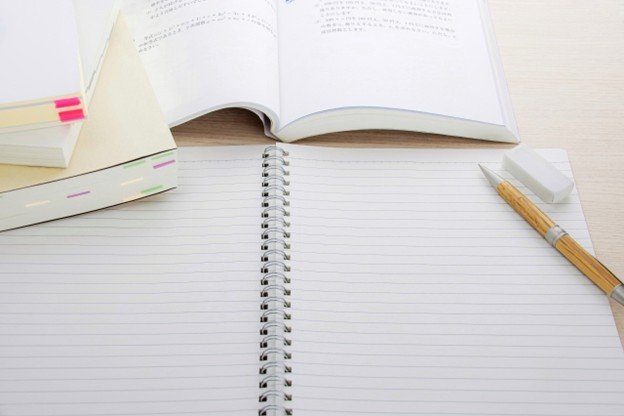
ここでは介護食アドバイザー資格取得に必要な試験の仕組み、通信講座での学習の進め方、費用をわかりやすくまとめます。
受験資格
認定教育機関で行う全カリキュラムを修了した方が対象です。年齢、学歴、職歴、調理や介護経験は問われず、誰でも受講可能です。
介護食アドバイザー資格は独学で取得できる?
資格取得には、JADP指定の認定教育機関(主に通信講座)で行う全カリキュラムの修了が必須です。修了後は在宅受験で試験を受け、合格者には「JADP認定介護食アドバイザー®」の資格が付与されます。
学習の流れ(カリキュラム)
認定教育機関 での学習はテキストが主で、学習中の質問はスマホでの確認となります。
また、学習は以下の流れで進められます。
1.基礎知識の習得:高齢者の心理や生理機能の老化、栄養学、介護食の基礎知識、高齢期の病気と食生活
2.家庭での調理実践:軟菜食・ソフト食などの作り方
3.添削課題:理解度を確認し、苦手分野を重点学習
4.修了試験:理解度を評価し、合格者に資格を認定
1日約15分の学習時間で、目安として3か月で修了可能とされています。家庭や仕事と両立しながら無理なく進められるカリキュラムで運用しているのも特徴の一つです。
介護食アドバイザーの試験情報と難易度

ここでは介護食アドバイザーの試験にまつわる情報について以下のとおりまとめています。
試験形式と合格基準
試験は基本的に在宅で実施。受験資格の確認・申し込み後、検定試験問題が自宅に発送されます。テキストを参照しながら解答できるため、暗記や時間制限の負担が少なく、初心者でも取り組みやすい試験です。合格基準は得点率70%以上です。
費用
通信講座費用 :約7万~9万円が目安(学習サポート期間で変動あり)
試験受験料 :5,600円(税込)
※2025年9月10日時点の情報
介護食アドバイザー資格の活かし方

介護食アドバイザーの資格は、家庭での介護から施設での食事提供、さらにキャリアアップまで幅広く活かせます。学んだ知識や技術を実生活に直結させられる点が、この資格の大きな魅力です。
家庭介護や日常の食事作りで
家族のために介護食を作る際、誤嚥を防ぎつつ栄養をしっかり摂れるよう工夫することができます。また、食事の見た目を工夫して「食べる喜び」を支えることができるため、家庭介護をより充実させられるでしょう。
介護施設や病院など現場で
介護職員や調理スタッフとして働く場合、介護食の専門知識を活かして利用者に合わせた食事を提供できます。施設にとっても「資格を持つスタッフがいる」ことは、信頼性の向上につながります。
就職・転職やキャリアアップへの可能性
福祉施設や高齢者向け事業では、介護食に関する知識を有する人材は貴重です。資格を取得しておくことで採用時のアピール材料となり、キャリアアップのチャンスを広げられます。調理部門だけでなく、介護職全般において評価されやすい資格です。
【まとめ】介護食アドバイザーは幅広く活かせる生活密着型資格

介護食アドバイザーは、家庭から介護現場まで幅広いシーンで役立つ実用的な民間資格です。国家資格のような専門的権限はありませんが、「安全でおいしい介護食を作る力」を学べる点が大きな魅力です。体系的な知識とスキルを習得することで、家族の健康を支えるだけでなく、介護施設や地域活動でも活躍の場が広がります。
高齢化社会において「食の支援」は、ますます重要になっています。介護食アドバイザーの資格を通じて、食事作りに自信を持ち、介護に関わるすべての方の生活をより豊かにしてみてはいかがでしょうか。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい