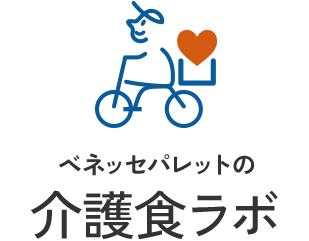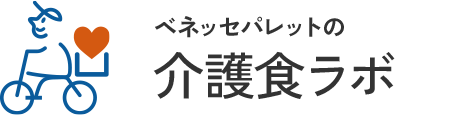2025 04 . 23
高齢者の栄養高齢者が気を付けたい食事と栄養摂取のポイント
高齢者における食事と栄養摂取について、必要な栄養素、食事の工夫についてご紹介します。健康維持に不可欠な情報をまとめ、看護師や介護士が参考にできる内容です。

高齢者にとって、適切な食事と栄養摂取は健康維持の鍵です。しかし、年齢と共に体の機能は変化し、必要な栄養素の摂取が難しくなることがあります。そこで、高齢者が健康的な食生活を送るためのポイントを解説。ぜひ実際の介護現場での参考にしてください。

目次index
1.高齢者の栄養管理の重要性
高齢者は年齢とともに食事の楽しみを失いやすく、食欲も減退しがちです。さらに、歯の状態が悪化し、噛む力が弱くなると、食べ物の選択肢も減ってきます。その結果、エネルギーやタンパク質、ビタミン、ミネラルが不足しがちに。そのため、定期的な食事指導や栄養士のアドバイスを受け、栄養管理を実施することが重要です。
厚生労働省の栄養ガイドラインに沿う
厚生労働省の指標によると、65歳以上の高齢者に必要とされる1日あたりのエネルギー量は男性で約2400カロリー、女性で約1850カロリーとされています。また、たんぱく質は男性60g、女性50gとされており、ほかの世代と同様にバランスの取れた食事を提供することが健康維持には不可欠です。
高齢者の栄養不足
高齢者における栄養不足は深刻で、食べる量が減ることでエネルギーが不足し、その結果筋力の低下や免疫力の低下、骨の健康にも悪影響を与えていきます。たんぱく質が不足すると、筋肉の萎縮や体力の減少も進み、日常生活の質が低下します。さらに、ビタミンやミネラルの不足も認知機能の低下や骨粗しょう症のリスクを高めます。このため、介護現場では高齢者の食事メニューを工夫し、栄養バランスを重視した献立を提供することが求められます。
たとえば、エネルギー不足を防ぐためには、オリーブオイルやゴマ油をかける、ナッツ類やアボカドを取り入れるなど、脂質の摂取を意識的に増やすことが重要です。また、たんぱく質の補給には、鰹節やチーズを加えたお粥やスープ、さらには豆腐や卵を使ったメニューなども効果的です。
食事が1日3食摂れないときは

食事が3食摂れない場合は、間食で栄養を補うのも有効。間食には、高カロリーで栄養価も豊富なナッツやフルーツ、ヨーグルト、または食べやすいサンドイッチなどを選ぶと、不足しがちな栄養素の補給がしやすくなります。
2.食事における注意点
高齢者に適した食事を提供する際には、健康状態や口腔機能に応じた配慮が必要です。嚥下機能や噛む力が弱まることで、安全で楽しい食事の提供が困難になることがあります。
高齢者のお口の健康
高齢者の食事は、口腔内の健康状態と密接に関連しています。唾液の分泌量が減少すると、口腔内の環境が悪化し、むし歯や歯肉炎、さらには誤嚥性肺炎のリスクが高まります。唾液は口腔内を清潔に保ち、食べ物を飲み込みやすくする重要な役割を果たします。そのため、日常的な口腔ケアが必要です。
たとえば口が常に乾いた状態でいると、唾液の分泌がしにくく、食べ物を嚥下するのもしづらくなります。一方、口腔内が乾燥していなければ嚥下もしやすくなります。
水分をとる以外にも、口腔専用の潤滑ジェルや保湿クリームを使用することで、唾液の不足を補うことができます。
嚥下機能の変化と対策
嚥下機能の低下は、高齢者が直面する最も重要な課題の一つです。噛む力が弱くなると、食べ物を十分に口の中で潰せず、誤嚥やむせるリスクが高まります。嚥下機能の変化に対応するためには、食事形態や食材の選定が重要です。
たとえば、そしゃく嚥下力が弱まっている場合は、ペースト状の食事やスープ状の食材、やわらかく煮込んだ食材を使うことで、飲みこみやすくなり誤嚥を防ぎながら、食事を楽しんでいただくことができます。また、高齢者が好む食べやすい料理は、すり潰したポテトサラダやカレーライス、スパゲティのミートソースなどがあります。
さらに、食事のスピードや量を調整することで、無理なく食事ができる環境をつくることも欠かせません。
食事中の誤嚥を防ぐために

誤嚥は、高齢者にとって命に関わるリスクを伴うため、その予防が重要です。食事の際に誤嚥を防ぐには、食事形態だけでなく、食べる時間や食べ方にも工夫ができます。
栄養を摂ってほしいからと量をクリアするために、1回あたりの食事時間を長くすれば、それだけ疲れることに。過度な疲れは、そしゃくや嚥下能力を一時的に弱らせる可能性があるため、かえって誤嚥のリスクが増します。適度に休憩を入れる、1回量を減らして間食を取り入れるなども、効果的です。また、食事中の会話を減らし、食べ物に集中することも、誤嚥リスクの減少には欠かせません。食べる環境は明るく楽しくしたいところですが、無理な会話は避けて、安全面に配慮することも大切です。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
※記事中の写真・イラストは全てイメージです。
参考文献:公益社団法人 日本栄養士会「栄養ケア活動ガイド」
厚生労働省「日本人の食事摂取基準」、「栄養改善マニュアル(改訂版)」、「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理」
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。