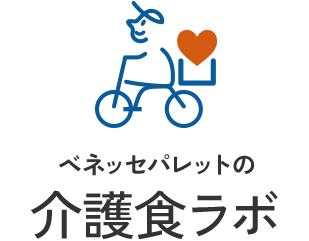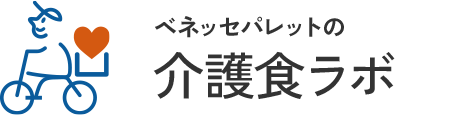2025 11 . 26
パン粥パン粥は嚥下食でいつから使える?学会分類2021に基づくレベル別の目安と基本の作り方
そしゃく・嚥下機能が低下した方も安心して食べられるパン粥の作り方と学会分類2021に基づくレベル別の目安を解説。家庭での調理や冷凍保存の工夫、栄養を補う方法も紹介します。

毎日の食卓でよく見かける食材として、多くの方がパンを思い浮かべるのではないでしょうか。ふんわりした仕上がりで食べやすそうに見えますが、実はそしゃく・嚥下機能が弱っている方にはそのままでは食べにくく、誤嚥のリスクがあります。
そんなときにおすすめなのが、パンを牛乳や出汁でやわらかく煮た「パン粥」です。
本記事では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「嚥下調整食学会分類2021」を参考に、パン粥をどのレベルから使えるかの目安と、基本の作り方、安全に食べるためのポイントを解説します。

目次index
パン粥と嚥下食の基本
パン粥を嚥下食として使うときは、「パンが嚥下食に向かない理由」と「注意点」を押さえておくことが大切です。
パンが嚥下食に向かない理由と注意点
パンは水分が少なく、口の中でまとまりにくいため、嚥下機能が低下している方には食べにくい食材です。噛んでもパサつきやすく、唾液だけでからめるにはまとまりにくいため、気管に入り込み、誤嚥の原因になることもあります。
このため、パンをそしゃく・嚥下機能が弱った方に提供する際には、牛乳や出汁などの液体で十分にふやかし、滑らかで飲み込みやすい状態に近づけることが必要です。
注意点
●誤嚥のリスクが高い方や、そしゃく力が弱い方は摂取を控える
●水分を加えてやわらかくしながら、食べる方の状態に合わせて食べやすさを調整する
また、パンはミミ(耳)部分を取り除いたやわらかいタイプを選ぶと、パン粥などにした際にもなめらかな仕上がりになります。
学会分類2021を参考にパン粥を使う場合
「嚥下調整食学会分類2021」では、食形態をコード0jからコード4までの段階で分類しています。パン粥は調理方法を工夫することで、幅広い段階に対応できるのが特徴です。
●コード1j相当:ゼリー状にかためる。均質に仕上がることでべたつかず、まとまりがよい。
●コード2相当:滑らかなペースト状にする。べたつかず、まとまりやすい。
●コード3相当:形のあるやわらかさにする。舌で押しつぶせば、口の中でまとめやすい。
嚥下状態が不安定な方は、ミキサーで滑らかに仕上げた後に、ゼリーの素やとろみ剤で軽くとろみをつけると口の中でまとまり、食べやすくなります。
段階別の特徴は、「嚥下食の分類まとめ|学会基準と実務での活用」の記事も参考にしてください。
パン粥の基本の作り方とポイント
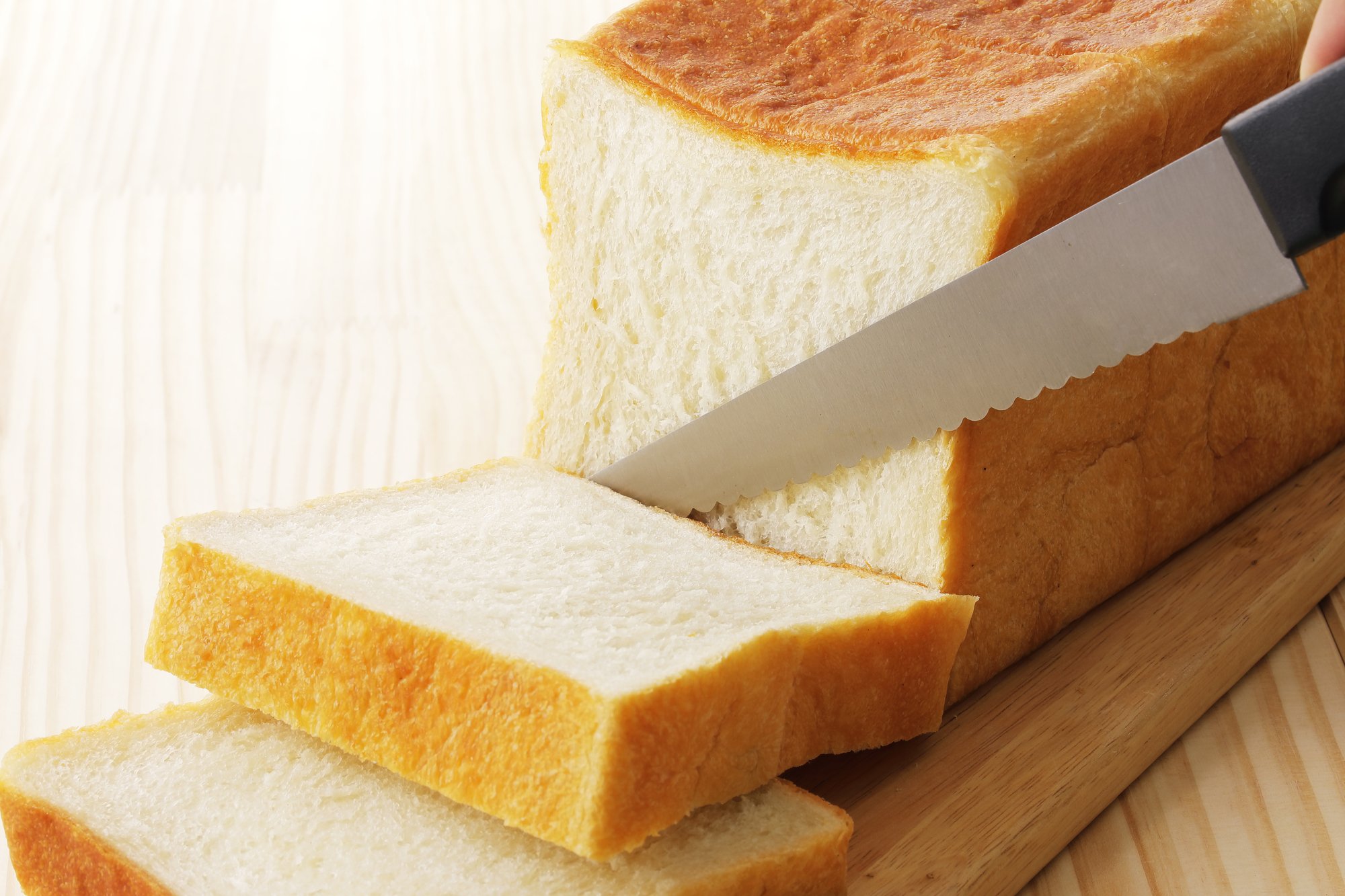
パン粥をおいしく、そして安全に調理するためには、パンの種類や液体の使い方、加熱方法が大切です。
パンの種類と下ごしらえ
パン粥には、耳部分を取り除いたやわらかい食パンを使うのが基本です。全粒粉やバターが多く含まれているタイプを避け、プレーン仕立てでしっとりしたパンを選びましょう。パンは小さくちぎってから、牛乳や出汁などの液体に十分に浸します。
また、パン粥はパンや浸す液体の種類で風味を変えることも可能です。
●牛乳で煮る:まろやかでコクのある味わいに
●出汁で煮る:やさしい和風仕立てに
ゆっくり加熱する
パン粥を作る際、パンを液体にしっかり浸してから加熱することで、均一かつやわらかく仕上げることができます。煮る際は焦げつかないように弱火でゆっくりと、ヘラで混ぜながら全体を均一に保ちましょう。加熱中に汁気が少なくなった場合は、牛乳や出汁を少しずつ足して調整します。嚥下状態に合わせて、やわらかさやまとまりを調整し、食べやすい状態に仕上げます。
パン粥の基本の分量や煮込み時間を変えた調理法、そしゃく・嚥下機能に応じたパンの大きさなど、パン粥の作り方について詳しくは「【高齢者向け】パン粥とは? 基本の作り方とポイントをご紹介」もご覧ください。
安全に食べるための工夫
パン粥を嚥下食として提供する際は、調理だけでなく、食べる環境や姿勢にも工夫が必要です。例えば、少量ずつゆっくりと食べることや、適温で提供することなどの気遣いが誤嚥予防につながります。
レベル別のパン粥例
ここで嚥下調整食学会分類2021に基づき、代表的なレベルのパン粥例を紹介します。
コード1j(嚥下訓練食1j):パン粥ゼリー
耳を落とした食パンを小さく切り、ゼリーの素と水をミキサーで撹拌(かくはん)した後、牛乳を加えて混ぜ、加熱してゼリー状にかためます。でんぷんのべたつきを抑え、滑らかでまとまりやすく、嚥下訓練や初期の嚥下食にも使いやすい形態です。
コード3(嚥下調整食3):パン粥つぶし
耳を落とした食パンを小さく切り、牛乳などの液体とともに電子レンジで加熱します。加熱後、フォークなどで全体をつぶして、やわらかくまとまりのある状態に仕上げます。形はかすかに残りますが、スプーンで軽く押すとつぶれる程度に仕上がるため、歯ぐきでつぶせる方に適しています。
在宅・介護での応用

パン粥は手軽に作れるだけでなく、家庭でも作りやすい嚥下食です。栄養面の補強や保存方法に工夫を施すことで、日常の食事に無理なく取り入れられます。
栄養を補うための食材の組み合わせ
パン粥の栄養素は炭水化物が中心になりやすいため、たんぱく質やカルシウムを含む食材を組み合わせることで、不足しがちな栄養を補えます。例えば、牛乳や豆乳で煮る、卵やすりつぶした豆腐、ヨーグルトを加えるなどの工夫がおすすめです。
また、粉ミルクや栄養補助食品を少量加えることで、エネルギーやたんぱく質を効率よく摂取できます。
アレンジの工夫については、以下の記事も参考にしてみてください。
「いつもの味に一工夫!パン粥のアレンジ方法」
家庭でも続けやすい!保存と解凍のコツ
パン粥は1回分ずつを小分けにして冷蔵・冷凍どちらでも保存が可能です。食べる際は、電子レンジや鍋で再度しっかりと加熱し、必要に応じて水分を足したり、とろみ剤でなめらかさを調整しましょう。保存方法を工夫することで、在宅ケアや施設でも、調理の負担を軽減できます。
〈保存の目安〉
冷蔵:1日程度
冷凍:1か月程度
※保存期間はあくまで目安です。なるべく早めに召し上がることをおすすめします。
〈解凍・加熱のポイント〉
・召し上がる際は、鍋や電子レンジで全体がしっかり温まるまで加熱してください。
・鍋で加熱する場合は焦げないよう、混ぜながら温めましょう。
・とろみ剤やゼリーの素などを使ったパン粥は、保存方法や加熱方法をメーカーに確認すると安心です。
【まとめ】パン粥を上手に取り入れて食事の幅を広げよう
パン粥は、そしゃく・嚥下機能が低下している方にとって「パンが楽しめる」だけでなく、「おいしく栄養補給ができる」機能的な嚥下食でもあります。学会分類2021を参考に、その方の状態に合わせて形態やとろみを調整し、活用してみてください。
調理の工夫次第で、パン粥は朝食や間食にも活躍します。「食べる喜び」を大切にしながら、無理のない範囲でパン粥を取り入れてみましょう。
※記事掲載の写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
【参考文献】
日本摂食嚥下リハビリテーション学会|嚥下調整食分類 2021
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf

あわせて読みたい