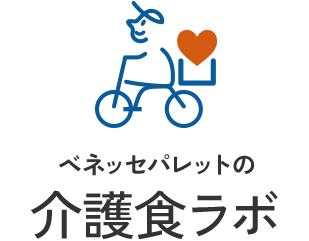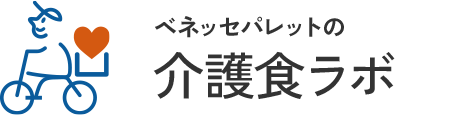2025 09 . 17
介護の基礎知識ミキサー食とペースト食の違いとは? 特徴・作り方・用途のポイント
高齢者やそしゃく嚥下機能が不安な方向けに、ミキサー食・ペースト食の違いや特徴、作り方、食感や水分調整などの調理の工夫を解説。安全でおいしく食べやすい介護食のポイントも紹介します。

そしゃく嚥下の力が弱まった高齢者や、病気・けがの影響で噛むことや飲み込むことが難しい方にとって、食事形態の工夫をすることは非常に大切です。介護現場や病院、在宅介護の場でよく耳にする「ミキサー食」と「ペースト食」。見た目は似ていますが、嚥下や調理方法、利用者への適応には明確な違いがあります。
本記事では、両者の違いを分かりやすく解説し、安全でおいしく食べてもらうための工夫についてもご紹介します。

目次index
ミキサー食とペースト食の違いとは

ミキサー食とペースト食は、食材を撹拌(かくはん)してなめらかにする点は共通ですが、水分量や粘り具合、口の中でのまとまり方は異なります。そういった観点から、利用者のそしゃく、嚥下のしやすさに応じて選ぶことが大切です。
学会分類との対応
ミキサー食は、介護食の中でも流動性が高い食事形態です。厳密な決まりはありませんが、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2021では、嚥下調整食2(コード2-1、コード2-2)に該当します。嚥下調整食2には、ピューレ、ペースト、ミキサー食などがあります。ベタつき(付着性)が少なく、かつまとまりやすく、スプーンですくって食べられるため、噛む必要はありません。
2-1:コード2の中でもなめらかで均質なもの。舌でまとめられる程度のかたさで、口腔内操作が弱い方に向きます。
食品例:粒がなくベタつかないペースト状の重湯や粥
2-2(ミキサー食に相当):コード2の中でもやわらかい粒などを含む不均質なものも含む。実務上は、2-2に相当する食事を「ミキサー食」と呼ぶことが一般的です。
食品例:やや粒があるがやわらかく離水もなくベタつかない粥、温泉卵
ミキサー食の特徴
ミキサー食は、そしゃく嚥下の機能が低下している方でも食べやすいよう、調理した食材をミキサーやブレンダーにかけてペースト状または液体状にした食事です。「ペースト食」「ピューレ食」「ブレンダー食」と呼ばれることもあります。水分が多く液状になりやすいため、そのままの状態で食事を提供すると誤嚥のリスクがあります。とろみ剤を加えて適度な粘度に調整し、スプーンですくって口の中でまとまりやすい形状にすることが必要です。
▶ミキサー食導入を検討している方はこちらも参考にしてください。
「ミキサー食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
ペースト食の特徴
ペースト食は、ミキサー食の中でも水分量を少なめにして口内でまとまりやすくした形態です。ミキサー食より水分が少ないのが特徴で、舌や口腔内の操作が弱い方でも安全に食べられるように作られています。
使い分けの目安
利用者のそしゃく嚥下機能に応じて食事形態を選びます。ただし、単純な分類で判断するのではなく、医師の確認や嚥下評価を踏まえたうえで調整することが重要です。
|
食事形態 |
特徴 | 向く人 |
| ミキサー食 | 水分多め・なめらか | そしゃくは難しいが飲み込む力が比較的保たれている方 |
| ペースト食 | 水分少なめ・まとまりあり | 舌や口腔内の動きが弱い方 |
▶その他の嚥下食との違いについて、こちらもご確認ください。
「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」
ミキサー食とペースト食の作り方・調理の工夫

そしゃくや嚥下機能が弱まった方でも、安全においしく食事を楽しめるよう、調理時にはいくつかの工夫が必要です。
下記6つの観点から、ミキサー食やペースト食の作り方のポイントをご紹介します。
● 食材選び
● 食材の下ごしらえ
● 水分量となめらかさの調整
● 誤嚥防止
● 食欲を引き出す盛り付け
● 味見の重要性
1. 食材選びのポイント
ミキサー食やペースト食には繊維が少なくやわらかい食材が向いています。
適している食材:
小松菜・ほうれん草など葉物野菜、にんじん・大根などの根菜、芋や豆などデンプン、鮭・赤魚など脂肪分が比較的多い魚
適さない食材:
ごぼうや小松菜の茎など繊維質の多い野菜、タコ・こんにゃくなど弾力のある食材、脂肪分の少ない魚や肉
2. 食材の下ごしらえのポイント
ミキサー食やペースト食を作る際の食材の下ごしらえのポイントは、以下にまとめています。
● 肉や魚の脂肪・筋を取り除く
● 蒸す・ゆでる・煮るなどでやわらかく加熱
● 色味を意識して組み合わせ、見た目で食欲を刺激
● 食材を均一な大きさに切り、加熱ムラを避ける
● 水分を調整して仕上がりのなめらかさやまとまりをコントロール
3. 水分量となめらかさ調整のポイント
ミキサー食は、だし汁や牛乳を少しずつ加えて撹拌し、飲み込みやすい濃度に調整します。ペースト食は、水分を加えすぎず、口内でまとまる状態に仕上げるのがポイントです。いずれも必要に応じて水溶き片栗粉や市販のとろみ剤を加えることで、そしゃく嚥下しやすい粘度に調整します。
4. 誤嚥を防ぐポイント
水分が多すぎると気管に流れ込みやすく危険です。ゆっくり流れる粘度に仕上げるよう、調理者の工夫が欠かせません。 ここではかぼちゃを例にして、工夫するポイントをまとめています。
かぼちゃを使った例:
● ミキサー食:ゆでたかぼちゃを撹拌し、だし汁でのばした後、溶き片栗粉または市販の とろみ剤を使ってとろみをつけます。スプーンですくったときに、ポタッと落ちる程度が目安です。
● ペースト食:ゆでたかぼちゃの水分を軽く切って撹拌し、少量のだし汁ととろみを加えます。 スプーンですくった際に形が少し残る程度に仕上げることで、口内でまとめやすく誤嚥リスクを抑えます。
※提供時には、医師や栄養士、言語聴覚士の指導のもとで、利用者の状態に合わせて調整してください。
5.食欲を引き出す盛り付けのポイント
ミキサー食やペースト食は形態が単調になりやすいため、盛り付けで工夫すると印象が大きく変わります。 ポイントは以下のとおりです。
● 色の異なる食材を分けて盛り付ける
● 出来上がった食事にケチャップやソースで模様を描く
● ハーブやごまを少量あしらう
▶盛り付けの詳しい例は、こちらの記事をご覧ください。
「見た目にもおいしい!ミキサー食の盛り付け例を紹介!」
6. 味見の重要性
調理者自身が味見をすることで、薄味になっていないか、塩分や香りの調整ができます。水分を加えると味が薄まるため、必ず確認しましょう。
● しょうゆや味噌、だしの風味を活かすと、嚥下調整食でも満足感のある味わいに
● 「食事は楽しみ」だということを意識し 、味・見た目・食感を総合的に整えることが大切
ミキサー食とペースト食の違いまとめ表
ミキサー食とペースト食の違いについて、以下の表にまとめました。実際の食事形態は施設や病院の方針、利用者の嚥下機能によって調整が必要です。
| ミキサー食 | ペースト食 | |
| 形状イメ―ジ | 液状・ポタージュ状に近い | 水分少なめでまとまりがある |
| 水分量 | 多め(だし汁や牛乳でのばす) | 控えめ(まとまりを重視) |
| 食べやすさの特徴 | なめらかで飲み込みやすいが、水分が多いと誤嚥しやすい | 舌でまとめやすく、誤嚥予防につながりやすい |
| 対象 | そしゃくが難しいが、ある程度飲み込みができる人 | 舌や口唇の動きが弱い人 |
| メリット | 液状でなめらかに仕上がるため、嚥下がしやすく、家庭でも作りやすい | 形が整いやすく、見た目もきれいにまとまっているため、誤嚥リスクを抑えられる |
| 注意点 | 水分を加えすぎると誤嚥リスクが高まるため、とろみの調整が必要 | 水分量やとろみの調整が必要 |
【まとめ】ミキサー食とペースト食を正しく理解して活用しよう

ミキサー食とペースト食はどちらも、そしゃく嚥下力に合わせて食べやすく工夫された介護食です。ミキサー食は水分を加えてなめらかにすることで飲み込みやすさを重視しており、一方、ペースト食はミキサー食の一種として、さらにきめ細かくまとまりのある状態に仕上げられた食事です。調理時の下ごしらえや水分量の調整、盛り付けや味付けの工夫を行うことで、安全性だけでなく美味しさや食欲の促進にもつながり、食べること本来の喜びも味わうことができます。ぜひ本記事を参考にしてみてください。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい