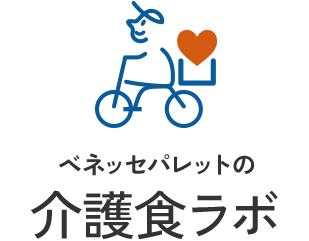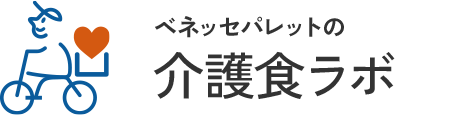2025 11 . 26
高齢者の栄養嚥下食メニューコンテスト|受賞レシピから学ぶ調理の工夫と傾向
嚥下食メニューコンテストの受賞レシピから、家庭や施設で活かせる調理の工夫を紹介。見た目や味、栄養バランスへの配慮も解説します。

高齢化社会に伴い、そしゃく・嚥下障害のある方でも安全に、かつおいしく食事を楽しめることが求められています。こうした中で注目されるのが、嚥下食の技術や創意工夫を競う「嚥下食メニューコンテスト」です。
本記事では、受賞レシピの特徴や調理の工夫、最近の傾向を紹介し、施設や病院、家庭での活用につなげるポイントを解説します。

目次index
嚥下食メニューコンテスト・レシピ大賞とは
嚥下食メニューコンテストは、「おいしく安全に食べられる食事」の普及を目的に開催。見た目や味つけ、栄養バランスなどが評価され、高齢者施設や家庭での実践に役立つ知識や技術を共有する場として注目されています。
嚥下食について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」
「嚥下食3(コード3)とは?嚥下調整食の分類と食事例&調理ポイント」
主な開催団体と応募資格
コンテストの主催者は協会や企業、市民団体など、多岐にわたります。応募対象には、全国の病院・福祉施設・大学・調理師専門学校のほか、一般の参加者が開発したメニューが含まれる場合もあり、家庭レベルでの工夫が評価されることもあります。多様な背景の参加者たちが工夫を凝らすことで、実践的かつ新しいアイデアが広がるのも大きな特徴です。
応募方法・評価基準のポイント
コンテストへの応募では、レシピや完成写真、開発の背景などを提出します。メニューの開発目的や地域性、調理工程のポイント、栄養や食形態の情報も評価の対象です。味つけや見た目、食べやすさへの工夫が重視され、家庭や施設で応用できるアイデアが高く評価されます。
応募の評価基準例は以下のとおりです。
応募の評価基準例
●見た目:彩りや盛り付けの工夫
● 味 :風味や調理法によるおいしさ
●栄養バランス:たんぱく質やビタミン・ミネラルなどを含めた全体のバランス
●安全性:噛みやすさ・飲み込みやすさ
●独創性:新しいアイデアや地域性の表現
受賞レシピの公開
受賞したレシピは家庭や施設で参考にできる内容として公開され、現場での技術普及にも役立てられます。
過去の受賞レシピから読み解く嚥下食の特徴
これまでの受賞レシピには、家庭や施設で活かせる工夫が随所に見られます。食材の選び方や調理法、盛り付けや彩りなど、参考になるポイントが多くあります。これらを押さえることで、日常の食事づくりや施設での提供にも活用しやすくなります。
よく使われる食材・調理法
過去の受賞レシピを分析すると、嚥下しやすさと栄養価の高さを意識した工夫が目立ちます。
●食 材:鶏肉や白身魚、卵、豆腐など、高たんぱくで嚥下しやすい食材が中心に用いられています。必要に応じて、野菜も組み合わせ、栄養バランスに配慮した構成になっています。また特色を生かした食材を取り入れることで、郷土色や風味の変化を楽しめるメニューもあります。親しみやすさや食材の個性を感じられる工夫が施されています。
●調理法:蒸す・煮る・焼くといった基本調理に加え、ムース化やゼリー化など、食べやすさを重視した工夫が取り入れられています。加熱や食感の調整によって、見た目や味わいも楽しめます。
見た目と味を工夫した受賞レシピ
受賞レシピでは、普通食に近い見た目を意識した工夫も見られます。また、色鮮やかな食材を用い、盛り付けや器の工夫で視覚的な満足度を高めています。食べやすさだけでなく、彩りや形状への配慮も行われており、高く評価されています。
嚥下食をおいしく見せるポイントと調理技術

受賞レシピの工夫は、施設での提供に役立つ内容が中心ですが、家庭でも応用できる点が多くあります。見た目や食感、栄養への配慮をすることで、嚥下食でも食事の楽しさや満足度を高めることが可能です。さらに、市販のとろみ剤やゲル化剤を活用することで、調理や盛り付けの工夫も効率的に行えます。
嚥下食の作り方とポイント
受賞レシピの評価には、各食形態の特徴や調理のポイント、注意点を押さえておくことが必要です。
以下の記事では、ミキサー食やペースト食、ムース食、軟菜食の作り方や調整のポイントを解説しているので、併せてご確認ください。
「ミキサー食とペースト食の違いとは? 特徴・作り方・用途のポイント」
「ムース食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
「軟菜食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
ムース化・ゼリー化・とろみ調整のコツ
ムース化やゼリー化、液体のとろみ調整を行う際は、食材の性質に応じて適切なゲル化剤やとろみ剤を選ぶことがポイントです。例えば、果物や野菜は寒天やゼラチンなどのゲル化剤でかためる、汁物やソースにはキサンタンガムなどのとろみ剤を使うなど、飲み込みやすさと食べ応えのバランスを意識することで、食べる方の満足度や評価の向上につながります。
ムース食やゼリー粥の具体例や作り方のポイントは、以下も参考にしてみてください。
「ムース食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
「嚥下食レシピ ゼリー粥基本の作り方からアレンジまで」
彩りや盛り付けで食欲を引き出す工夫
色味を三色使ったりグラデーションを施したりすることで、見た目にバリエーションを持たせることで食べる楽しみにつながります。色の使い方の工夫は食材に限ったことではありません。器の選び方やトッピングで季節感を演出することも可能です。「おいしそう」「食べてみたい」と感じてもらえる見た目の楽しさは、食事への意欲を高める大切なポイントです。
高齢者の食事や栄養について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
「高齢者が気を付けたい食事と栄養摂取のポイント」
コンテストや日常調理にも活かせる嚥下食セミナー
嚥下食メニューコンテストは、介護食の創意工夫を発表する場です。家庭や施設で安全に活用するための基礎知識や調理技術は、栄養士・介護職・調理師向け、または家族介護を行う一般の方向けの講座やセミナーで学べます。
講座は、嚥下食に関わる協会や自治体、企業などで行われているため、興味のある分野やテーマの講座を探してみるとよいでしょう。
嚥下調整食学会分類2021の理解
講義では、最新の「学会分類2021」に沿って、食形態やとろみの段階を体系的に整理しながら学びます。ペーストやムース、ゼリーの実例で食感や見た目の違いを体感し、分類の考え方や調理の工夫、飲み込みやすさの判断ポイントの理解を深めることができます。
調理技術の向上
蒸す・煮るなどの基本調理に加え、ムース化やゼリー化など嚥下のしやすさを考慮した加工法を習得できます。食材ごとの加熱やテクスチャー調整のコツを身につけることで、施設でも家庭でもより実践的な対応が可能になります。
調理機器を活かした実践技術の習得
スチームコンベクションオーブンやフードプロセッサーなどを使った技術を体験できる講座も設けられています。機器メーカーや食品企業との共同セミナーでは、現場で応用できる調理法のヒントも得られる場となっています。また、介護食に関する知識をさらに深めたい場合は、資格取得を通じた学びもおすすめです。
関連資格に関する情報は、以下の記事でご紹介しています。
「介護食アドバイザー資格とは?メリット・取得方法・活かし方を徹底解説」
「介護食士とは?資格の取り方・仕事内容をわかりやすく解説」
嚥下食の普及と社会的意義

嚥下食は「単なる栄養補給」ではなく、人生を豊かにする「食べる喜びを支える工夫」です。講座やセミナーで学んだ知識や技術を現場で活用することで、より多くの人が安全でおいしい食事を体験できる環境づくりにつながります。
高齢者施設・病院での嚥下食活用事例
高齢者施設や病院では、見た目や味つけを工夫した嚥下食の提供が進んでいます。例えば、病棟全体で少量高カロリー食や味付け・食感を工夫したメニューを導入した病院では、患者の食欲が回復して、栄養摂取量や口腔衛生の改善につながった事例があります。
地域・企業による嚥下食の啓発活動や研究開発
企業と医療機関の連携による嚥下食の開発を進める事例も増加傾向です。また、市民向けの試食会や体験イベントを通じて、地域住民への啓発活動も活発に行われています。こうした取り組みをきっかけに、家庭での実践や地域コミュニティにおける共有が、嚥下食普及の鍵となります。
【まとめ】コンテストから広がる嚥下食の未来
嚥下食メニューコンテストは、技術や創意工夫を広く共有する場として、家庭・施設・病院での食事の質向上につながる取り組みです。見た目の美しさ、食べやすさ、栄養バランスに配慮することで、より多くの方が「おいしく安全に食べられる食事」を楽しめる環境づくりが進められます。今後も地域や企業、専門職の連携によって、嚥下食の普及と進化がさらに広がっていくことが期待されるでしょう。
※記事掲載の写真はすべてイメージです。
この記事の監修

栄養士
下口 貴正
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。
長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。
2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。