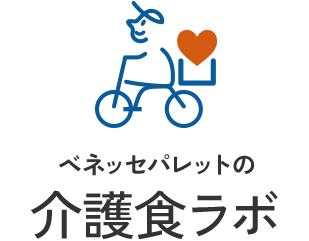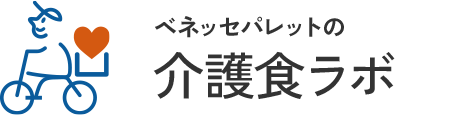2025 11 . 19
介護の基礎知識手作りできる嚥下食献立|家庭でもできる段階別工夫と調理のヒント
手作りする際の嚥下食の献立や調理の工夫を紹介。段階別の食材のやわらかさやとろみの付け方、温度や香り、盛り付けの工夫を通して、食べやすさや満足感を高めるポイントを解説します。

高齢者や嚥下機能に不安がある方の食事は、安全性が最優先です。しかし、安全性だけを意識し飲み込みやすさに偏ると、栄養や味付け、見た目がおろそかになり、食が進みにくくなることがあります。
そこで、家庭でも作れる、食べやすさや見た目に配慮した嚥下食献立のポイントを紹介します。

目次index
嚥下食の基本|献立作りの前に知っておきたいこと
嚥下食を作る際は、食べやすさだけでなく、栄養や見た目、食欲への配慮も必要です。安全で満足度の高い食事にするためには、まず嚥下食ならではの課題を理解しましょう。
●誤嚥やむせのリスク
食材のかたさや形、とろみ付けの調整が不十分だと、むせや誤嚥の原因になります。
●栄養バランスの偏り
ミキサーにかけるために加水すると水分量が増え、見た目の量は増えても、栄養が薄まってしまうことがあります。さらに、量が増えたことで食べ残しにつながることもあります。
●食欲に関わる要素
彩りや香り、提供する温度などへの配慮が不十分だと、食欲の低下につながります。
●調理負担や調整の難しさ
嚥下食は個人ごとにやわらかさやとろみを調整する必要があるため、手作りとなると手間がかかります。
高齢者の食事や栄養に関する課題やリスクについては、以下の記事も参考にしてください。
「高齢者の栄養失調が起こる要因と対策」
「高齢者の低栄養を防ぐ 栄養管理のポイント」
「高齢者の栄養の管理ポイント たんぱく質とカロリーを効率的に補う方法」
嚥下食の段階別分類と献立の目安
安全で食べやすく、栄養バランスのとれた献立にするには、食材のやわらかさや形状、水分量を利用者の状態に応じて調整することが大切です。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会の2021年分類では「コード0~4」に分かれており、段階ごとのかたさや形の目安を知ることで、安心して食べられる嚥下食づくりにつながります。
段階に応じた食形態の特徴と献立作りのポイント
●コード0(嚥下調整食品0j/0t)
・対象:嚥下機能が著しく低下している方(評価・訓練段階にある方)。
・特徴: 0j/ゼリー状。少量で丸呑み可能。残留しても吸引しやすい。
0t/とろみ状。咽頭通過が遅い方に適応。
・献立作りのポイント:水分や栄養を意識し、飲みやすい組み合わせに。
食品例)お茶ゼリー、果汁ゼリー、市販の嚥下訓練用ゼリー、とろみをつけた飲料
●コード1(嚥下調整食1j)
・対象:飲み込みや舌での移送が困難な方。
・特徴:ゼリー・プリン・ムース状で均質。離水が少なく、なめらか。
・献立作りのポイント:主食・主菜・副菜をそろえ、色味を工夫して単調にならないように。
食品例)卵豆腐、重湯ゼリー、ミキサー粥ゼリー、市販のムースやゼリー
●コード2(嚥下調整食2)
・対象:口腔内で軽く操作できるが、そしゃくはほとんど行えない方
・特徴:ピューレ・ペースト状。均質なもの(2-1)や、粒入りやわらか食材(2-2)に分かれる。
・献立作りのポイント:あんやソースでまとめると味の変化がつけやすい、水分調整もしやすい。
食品例)粒なしペースト状の重湯・粥、やわらかい粒入り粥、野菜や魚のピューレ
●コード3(嚥下調整食3)
・対象:舌や口蓋(こうがい)間で押しつぶせる程度のそしゃく力がある方。
・特徴:やわらかく、口の中でまとまりやすく、多量の離水がない料理が中心。
・献立作りのポイント:主菜や副菜にとろみやあんを使う。食材を小さく切るなどの工夫で飲み込みやすくする。
食品例)五分粥、全粥、やわらかいハンバーグ煮込み、卵料理、あんかけ野菜
●コード4(嚥下調整食4)
・対象:上下の歯槽堤間で押しつぶせる程度のそしゃく力がある方。
・特徴:軽度の嚥下障害やそしゃく力低下に対応し、やわらかく均一な調理が基本。
・献立作りのポイント:通常のやわらかめ調理で煮物や卵料理など、食材ごとのやわらかさを意識。
食品例)全粥、軟飯、やわらかく煮た素材料理、卵料理
上記コード0からコード4までの詳しい解説や調理のポイントは、以下記事をご覧ください。
「嚥下(えんげ)食とは?その必要性と分類について」
【具体的な献立例】嚥下調整食3(コード3)の場合
ここでは、家庭で作りやすく、彩りや味付けの工夫がしやすいコード3を例に、1食分の献立と調理のポイントを紹介します。
1食の例)
●主食:全粥
●主菜:白身魚のとろみあんかけ
●副菜:なめらかかぼちゃのマッシュ
●汁物:とろみ付きすまし汁
嚥下調整食3(コード3)での各品目のポイント
コード3は、舌や口蓋(こうがい)間で押しつぶせるやわらかさが特徴です。手作りでも、食べやすさや見た目、風味に配慮して調理します。
●主食:全粥
水分を含ませてやわらかく炊き、舌で押しつぶしやすい状態にします。粘度や水分量を調整して、飲み込みやすくします。必要なとろみがつかない場合は、とろみ剤などを活用します。
●主菜:白身魚のとろみあんかけ
魚はほぐして加熱し、あんかけなどでとろみをつけることで口に運びやすくします。あんにだしや細かく刻んだ野菜を加えると、風味も増します。
●副菜:かぼちゃのマッシュ
やわらかく煮てマッシュ状にし、舌で押しつぶしやすくします。少量のだしや油で味を調えると食欲も高まります。
●汁物:とろみ付きすまし汁
とろみをつけてむせにくくし、水分補給や食欲の刺激に役立ちます。提供時の温度は飲み込みやすい適温に調整しましょう。
具体的なコード3の特徴を知りたい方は「嚥下食3(コード3)とは?嚥下調整食の分類と食事例&調理ポイント」もご覧ください。
また、ミキサー食やペースト食、ムース食、軟菜食の作り方や調整のポイントについては以下で解説しているので参考にしてください。
「ミキサー食とペースト食の違いとは? 特徴・作り方・用途のポイント」
「ムース食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
「軟菜食とは?作り方のポイントや注意点を解説」
家庭で手作りしやすい調理の工夫

嚥下食を作る場合、毎日の調理負担を軽くすることが大切です。食材の下ごしらえや作り置きの工夫により、手間を減らしつつ、安全で栄養バランスのとれた食事を提供できます。
下ごしらえと作り置きで手間を減らす
野菜はマッシュやピューレ、肉や魚はそぼろ状にして冷凍保存するなど、下ごしらえを事前にしておくと効率的です。必要な分だけ解凍してすぐ使えるだけでなく、まとめて調理することで、作業時間も短縮できます。また、小分け保存することで、風味や栄養を保った状態で提供できます。
肉の種類や調理のポイントについては、以下の記事も参考にしてください。
「【高齢者向け】肉を使った嚥下食」
市販品や冷凍食品を活用して嚥下食を作る
すべての嚥下食を手作りする必要はありません。市販のやわらか食や冷凍食品、レトルト食品を組み合わせることで、栄養バランスを保ちながら、調理の負担を軽減できます。忙しい場合は、宅配弁当の活用も有効です。
高齢者向け弁当の利用の際のポイントや注意点については、以下を参考にしてください。
「高齢者向け宅配弁当の選び方|施設導入の際のポイント」
「忙しい施設必見!高齢者向け冷凍宅配弁当サービスの導入5つのメリットと活用法」
また、市販品を選ぶ場合は、ユニバーサルデザインフード(UDF)や特別用途食品を理解すると、利用者に合った嚥下食を選びやすくなります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
「嚥下食の分類まとめ|学会基準と実務での活用」
食べやすさとおいしさを高める工夫
嚥下食では、とろみや温度、香り、見た目に工夫を加えることで、食べやすさやおいしさを保つことができます。
とろみの調整
嚥下食をより食べやすくするためには、とろみの調整が不可欠です。水溶き片栗粉は少しずつ加え、加熱しながら粘度を確認して調整します。市販のとろみ剤を使う場合は、パッケージに記載されている分量を正確に計りましょう。
粘度の目安:
専門家(医師や言語聴覚士、管理栄養士など)に相談するのが基本です。簡易的には、学会の基準を参考にスプーンでとろみの状態を確かめる方法があります。
詳しい目安や分類については、以下の記事もご覧ください。
「嚥下食とは?その必要性と分類について」
香りの工夫
だしやごま油で香りを引き立てると食欲が刺激されます。酸味や辛味の調味料を少量加える、香味野菜を活用するなども効果的です。
温度の調整
温度は体温との差がおよそ20℃になるように調整すると、嚥下がしやすくなるといわれています。温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく提供することで、おいしさも保たれます。
冷たい料理:5〜10℃/温かい料理:60〜65℃
※料理内容や個人の嚥下しやすさに合わせて調整してください。
見た目の工夫
色や形
赤、緑、白など食材の色を組み合わせ、型抜きや小鉢を活用すると、食事全体が華やぎます。
盛り付け
主菜と副菜を分けて盛り付けると、見た目が整い、食事もしやすくなります。
ミキサー食の盛り付け例は、こちらの記事をご覧ください。
「見た目にもおいしい!ミキサー食の盛り付け例を紹介!」
【まとめ】安全でおいしい嚥下食献立を続けるために

嚥下食の献立では、食べる方の段階に応じた食材や調理法を選び、主食・主菜・副菜のバランスを意識することが重要です。さらに、下ごしらえや作り置きを活用し、粘度や食感、温度、香りに注意することで、食べやすく満足度の高い食事になります。盛り付けや彩りも工夫することで、見た目にも楽しめる嚥下食を提供していきましょう。
※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。
この記事の監修

管理栄養士
角 佐知子
献立作成、完全調理済み食品の開発に携わる。
ベネッセパレットにて、マーケティング部へ所属。現在、薬膳について、資格取得へ向け勉強中。
【参考文献】
日本摂食嚥下リハビリテーション学会|嚥下調整食分類 2021
https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf

あわせて読みたい